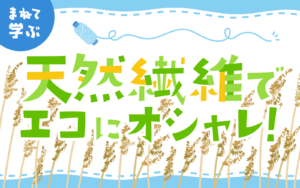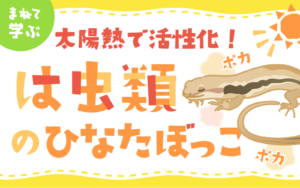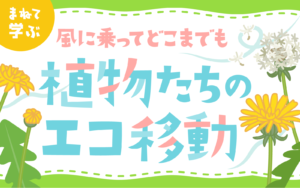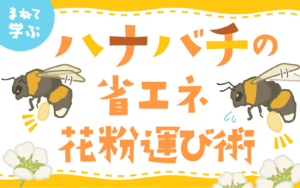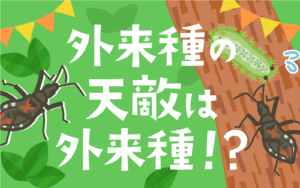日本で見られるカメムシの中では最大の大きさをもつ、キマダラカメムシ。東京や大阪などの大都市の街中でもごく普通に見られます。ですがこのカメムシ、実は外来種なのです。
キマダラカメムシってどんなカメムシ?
体長2cmを超えるカメムシです。広葉樹の樹液が主なエサです。漢字で書くと黄斑亀虫。その名の通り、背中に鮮やかな黄色の斑点(はんてん)がたくさんあります。キマダラカメムシによく似たいきものに、在来種のクサギカメムシがあります。キマダラカメムシとクサギカメムシの見分け方は背中、頭のスジ、体の後ろの方のシマシマで区別できます。

キマダラカメムシの成虫(Photo by 蓮見):背中の黄色の斑点、頭部の黄色い縦筋、体の後ろの方にある鮮やかな黄色と黒のシマシマが特徴です。

クサギカメムシの成虫(Photo by ウミスズメ):背中には黄色い斑点がありません。体の後ろの方にある、白っぽい灰色と黒色のシマシマが特徴です。キマダラカメムシに比べると少し小さいです。
キマダラカメムシは、幼虫もなかなかエキゾチックな見た目です。

キマダラカメムシの初令(しょれい:生まれて1度も脱皮していない)幼虫(Photo by Robert3298)

キマダラカメムシの2令(にれい:生まれて1回以上脱皮した状態)以上の幼虫(Photo by 直帰)
見つかる場所
暖かい季節は、公園や道路脇の街路樹の幹でよく見つかります。特に桜の木(ソメイヨシノ)の幹で見つかることが多いです。
寒い季節は、樹皮の隙間、雨戸や戸袋の隙間などで成虫越冬します。室内で見つかることも珍しくありません。
拡大状況
キマダラカメムシの海外の分布域は、東アジアから東南アジアにかけての地域です。日本で最初に見つかったのは江戸時代。その後150年間も見つかってこなかったのですが、1934年に長崎で再発見されました。2000年頃から急速に分布が拡大し、現在では関東より北の地域でも見つかるようになりました。南方系カメムシであるキマダラカメムシの拡大には、地球温暖化が影響している可能性が考えられます。
見つけたら気候変動いきもの大調査(バイオーム)に投稿を!
キマダラカメムシを見かけたら、バイオームにぜひ投稿してください。みなさんからの投稿により、現在の分布域を明らかにしたいと思います。
「いきものエコ診断」をやってみよう!
あなたの行動に近い「エコな生態を持ったいきもの」が診断できます。結果をSNSでシェアしてヒトといきものに優しい環境づくりの輪を広げていきましょう!
いきものエコ診断へ